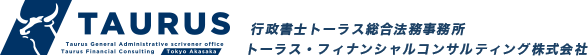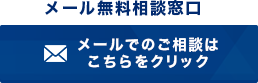金融商品取引業とは
 このページの目次
このページの目次
金融商品取引業の種別-登録金融機関業務-業として行うとは-証券規制の歴史
業態ごとの平成-証券-FX-信託受益権-資産運用ビジネス-金融商品取引法の成立-銀証分離とビッグバン
金融商品取引業種別各論-第一種金融商品取引業-第二種金融商品取引業-投資運用業-投資助言・代理業
その他-有価証券関連業-電子募集取扱業務-適格投資家向け投資運用業-適格機関投資家等特例業務-海外投資家等特例業務及び移行期間特例業務
金融商品取引業の種別
金融商品取引業とは、平成19年に証券取引法を改正して施行された、金融商品取引法2条8項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う業務です。
ただし同各号に掲げる行為のうち、金融商品取引法施行令第1条の8の6及び金融商品取引法第二条の定義に関する内閣府令第16条に掲げる「金融商品取引業から除かれるもの」は金融商品取引業から除外されています。
金融商品取引業は、既存の証券業、金融先物取引業(FX業者)、投資信託委託業、信託受益権販売業、投資顧問業(一任・助言)、ファンド業(当時は登録不要)等の複数の投資サービスに関連する業態を共通規制の下に置いたものです。
金融商品取引業は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の4種別から成り立っています。種別の違いは、行うことのできる業務内容の違いであり、種別間に、上位下位の概念はありません。
言い換えれば、第一種金融商品取引業のみの登録を受けていても、第二種金融商品取引業はできません。同じく投資運用業のみの登録を受けていても、投資助言・代理業は行うことができません。登録を受けていない業務をするには金融商品取引法第31条に基づく変更登録を要します。
これらに加えて金融商品取引業の補助的な業態として、第一種金融商品取引業者及び投資運用業者に所属する仲介専門の業態である金融商品仲介業が存在しています。
さらに、少人数プロ向けファンドに限り、本来は、第二種金融商品取引業に該当する自己私募業務と投資運用業に該当する自己運用業務を、金融商品取引業登録を受けずに届出のみで行うことのできる特例である適格機関投資家等特例業務も存在します。こうした集団投資スキームの自己募集業務は、証券取引法時代は原則として業登録が不要でしたが、金融商品取引法制下では金融商品取引業に位置付けられています。
また、金融商品取引法施行から15年以上が経過し、現代では、金融商品取引業の内部にいくつかの新しい業態が生まれました。
プロ投資家のみを対象として運用資産が少額(200億円)の場合に、登録要件の緩和が受けられる、「適格投資家向け投資運用業」、オンラインで少額の有価証券の取得申し込みを受けることに絞った業態である「第一種少額電子募集取扱業務」及び「第二種少額電子募集取扱業務」は、平成に生まれた制度です。
令和になってからも、所属業者を持たない新たな金融サービスのアレンジャーである「金融サービス仲介業」、我が国の国家戦略である国際金融センター構想に基づき新設された「海外投資家等特例業務」及び「移行期間特例業務」など、金融商品取引法施行時には想定されていなかった新しい業態が、法改正で、随時創設されています。
登録金融機関業務
金融商品取引業務は、基本的には金融商品取引業者が行っていますが、上記の金融商品仲介業者や金融サービス仲介業者の例外があります。
それ以外にも、銀行、信用金庫及び信用組合その他預金取扱い金融機関(金融商品取引法第33条に掲げる「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関」)は、一定の金融商品取引業務を、金融商品取引法上の登録金融機関として行っています。
世界恐慌の反省を受けて制定された伝統的な銀証分離(グラス・スティーガル法)の考え方を受け継いで、金融商品取引法第33条第1項は「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条、次条及び第二百一条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行ってはならない・・・」という出だしになっています。
とはいえ、金融ビッグバンを経て、こうした銀証分離の垣根は低くなっています。
銀証分離の例外は、同項の但し書きである「ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。」だけに留まらず、より広い銀証分離の除外規定が同2項に設けられています。
同2項では「前項本文の規定は、金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない」として修正されており、同第1号から同第6号まで、幅広い業態を登録金融機関業務として営むことが可能になっています。
なお、こうした登録金融機関業務には、金融商品仲介業に相当する業務も含まれますが、令和5年には金融商品仲介業務に係る登録金融機関業務に関して、大手地方銀行に対する行政処分が行われるなど、その業務の適合性の原則に照らした適切性に関しては、規制当局の厳しい目線が存在しています。
業として行うとは
金融商品取引法第2条第8項は、「この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(略)のいずれかを業として行うことをいう。」としており、業として行うことを要件としています。
業として行うとは、通説では「対公衆性」のある行為で「反復継続性」をもって行うものをいうと解されています。「対公衆性」や「反復継続性」については、現実に「対公衆性」のある行為が反復継続して行われている場合のみならず、「対公衆性」や「反復継続性」が想定されている場合等も含まれるとしています(平成19年金融庁パブリックコメントP35.No3)。
同パブリックコメントでは、100%親会社と子会社との取引であっても、一律に金融商品取引業から除外されるわけではないとしており(同No.4)、「業として行う」の該当要件は実務上厳格に解されています。
相対取引なら適法なのではないか、宅建業法や貸金業法等の他の業法を参照すれば、反復継続をしなければいいのではないか等と質問を受けることがあります。こうした事例では、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断する必要がありますが、経験的にはそうした照会は、多くの場合、登録が必要と思われるケースに該当します。
金融商品取引法に基づくのスキームにおいては、反復継続性のない一度きりの取引であるから適法という整理は実務上通用しません。金融商品取引業では、監督実務上、常に完全な適法性を求められるという意味で、グレー事案が跋扈している宅建業法や貸金業法等の法解釈とは距離があります。
他方、自己投資目的で有価証券の売買を行う個人や企業の行為は、対公衆性を欠くと解されており、金融庁も同パブリックコメントで自己のポートフォリオを改善するために行う「有価証券の売買」等は、基本的に「業として」(金商法第2条第8項柱書)行うものに該当せず、「金融商品取引業」に該当しないと回答しています(P39.No.25)。
しかしながら、自己のポートフォリオの改善のための投資は一般的に対公衆性を欠くというのがこの議論の前提(金融法委員会・金融商品取引業における「業」の概念についての中間論点整理P4)であり、対公衆性があれば、自己のポートフォリオの改善を目的とした投資でも金融商品取引業に該当すると解されています。
証券規制の歴史
我が国の証券取引法は、アメリカの連邦証券法(1933)、証券取引所法(1934)及び投資会社法(1940)を基本に、英米法をベースで立法されました。1947年に制定された後、1948年に全面改正されています。
こうした来歴のために、米国証券法は大陸法ベースの我が国の私法体系とは馴染みにくい特性を持っています。また、アメリカ証券法は、上記3法がベースになり、派生する複数の関連法規が存在します。ちなみに、アメリカで投資助言業務を規律する法律は投資顧問業法(1940)です。
日本では、証券取引法が基本原則となりそこから業法が個別に派生・発展したことにより、投資サービスに対する平成10年代半ばの業規制は、相当に複雑化していました。
当時は、証券取引法の他に、いわゆる投信委託業を規定した昭和26年証券投資信託法に基づく証券投信委託業、投資ジャーナル事件をきっかけに昭和61年に制定された投資顧問業法に基づく投資顧問業(助言及び一任)、昭和63年に制定され平成16年にFX業者を取り込む大改正のあった金融先物取引法に基づく金融先物取引業、大正より存在した信託業法に基づく信託受益権販売業など、制度が乱立していました。
業態ごとの平成
バブル崩壊以前の歴史に関しては、本筋と関係ないわりに長くなるので、こちらの記事にまとめています。
証券
平成期の証券業界は、短いバブルの絶頂を経て、冬の時代が長く続きました。
証券会社の平成規制史は、バブル崩壊後に次々判明した「飛ばし」、「握り」、「総会屋」及び「利益供与」に対する、業界と規制官庁の反省が原点にありました。ある意味、平成元年大納会に付けた日経平均38,915円のツケを、その後の30年かけて精算する歴史であったように思います。
平成9年半ばの大手都市銀行及び四大証券利益供与事件を経て、平成9年11月3日には三洋証券が倒産し、11月17日には潰れないはずの大手20行の一角であった拓銀が破綻。同24日に至っては当時の四大証券の一角、山一證券が自主廃業を発表しました。
さらに、監督官庁にも問題は飛び火。平成10年の大蔵省汚職は世論の激しい反発を招き、平成13年には中央省庁改革で財務金融が分離されるに至りました。
令和の現在、マトモな金融商品取引業者の間では、顧客に対する元本保証、損失補填、特別の利益の提供等は、「犯罪でありとんでもないこと」として認識されていると思います。バブル以前のVIP口座や元本補填の約束が普通に行われていた当時の証券業界の感覚は、現代には引き継がれていません。また、現代では金融行政も当時と比べてはるかに公正に行われています。
一方、平成不況にあえぐ中でも、次々と新しいビジネスが生まれました。
平成8年に橋本政権で打ち出された六つの改革の中でも、中核に位置付けられた金融システム改革による、いわゆる金融ビッグバンが開始されました。同年以降、いわゆる「ウインブルドン方式」の呼び声とともに、新規参入の促進、銀証分離の緩和、手数料自由化等が進められました。
平成10年の証券業の登録制移行により、デイトレーダー・ブームが始まるとともに、ネット証券会社(SBI証券、松井証券、楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券等)系の新興の証券会社が勃興しています。
また、90年代は外資系証券の存在感が急激に上昇しました。バブル崩壊時には今や伝説的な存在であるソロモン・ブラザーズをはじめとするアメリカ系証券会社の東京支店が膨大な収益を上げたことが報道されて話題になりました。
今ではほぼ死語ですが「ハゲタカ外資」という、バブル後の日本経済への過大評価を背景とする実態のない言葉が世間で広まったのも、この時代から2000年代前半にかけてです。
1997年の山一證券の破綻後には、メリルリンチ日本証券が山一證券の営業基盤を引き継いだことで、一般国民の間でも外資系証券会社への認知が高まりました。
外資系金融の存在感が高まる中で、1999年には欧州系銀行某社に対して、検査忌避や損失先送り商品を販売したことを理由に免許取消しが行われました。
こうした一連の流れを受けて、90年代から00年代にかけて、外資系金融は、従来のマイナープレーヤーとしての立場から、現在のような我が国の金融システムの中枢の一角を占め、かつ、規制監督上の責任も本邦金融機関と同様に負担するメジャーな存在へと転換していったといえます。
さらに、段階的な銀証分離の緩和により、90年代にはいわゆる銀行系証券会社も続々と誕生しています。金融商品仲介業制度の利用と併せて、銀行の証券業務への参入は、今も継続する大きな動きです。
平成19年の金融商品取引法改正により証券業は、事実上後述の金融先物取引業と統合された形となり、第一種金融商品取引業と整理されるようになりました。
ネット証券や投資銀行業務等で注目された00年代と異なり、令和の現代では、ある意味でオールドエコノミー化したといってもいい「証券会社」業態ではありますが、セキュリティ・トークン関連等のFINTECHビジネスをベースとして令和に入っても一定の参入需要があります。また、エクイティークラウドファンディング業者である第一種少額電子募集取扱業者も、証券会社の新たな派生形態といえます。
FX
FX業者は、平成9年の外為法改正による外国為替業務の自由化に端を発した業態です。FX業者は高い収益性を誇りつつ、OTC売買の特性から商品先物取引業系の会社が多数参入したことにより、当初、消費者保護とのハレーションも生みました。
ある意味、後年のロコ・ロンドン取引と同じ淘汰過程を歩んだといえますが、ロコ・ロンドン取引は、該当業者が現在ほぼすべて消滅している点に違いがあります。
平成10年代前半の最盛期には、今では禁止されている強引な勧誘により、現代には見ないような消費者被害も生じた時期すらありました。とはいえ、令和3年後半の現代、FX業務を行っている第一種金融商品取引業者には、もはや安定的な収益基盤を有する、良くも悪くもマトモな事業者以外は、ほぼ生き残っていません。
平成20年、我が国にとって、当初は対岸の火事と考えられていたリーマンショックの余波で、リーマン・ブラザーズをカバー先としていたFX業者に破綻事例が生じたことは、金融庁にとって衝撃であったとされます。消費者被害や業者濫立その他総合的に業界事情を勘案し、平成20年以降、FX業者の新規参入は、事実上不可能に近い厳格なハードルが課されています。
同年以降、外国為替証拠金取引に全くの新規で参入できたのは、大手、準大手金融グループのみであり、外資や新興企業にとって、店頭FX業務への新規参入はM&A以外に想定しがたくなっています。
また、既存業者にとっても、古くは信託保全義務化や段階的なレバレッジ規制に始まり、非対称スリッページ規制、スプレッド広告規制、レート保存義務及びストレステスト義務など、法令と協会規則が連動する形で徐々に業規制が強化されています。
現代、FX業界は成熟と安定のフェーズに到達しつつあり、かつてのような合従連衡の時代とは隔世の感があります。他方で、依然として一定の存在感を持つ、職業的な触法行為組織、すなわち反社会的勢力である無登録海外FX及びこれら違法業者のアフィリエイターや自動売買提供者等と称する反社共生者を根絶できていないのは、引き続きの金融規制上の課題といえます。
また、FX業務を主体とする証券会社を中心とし、海外の影響を受けて既存業務からいわば派生する形で、証券CFD、商品CFD及びバイナリーオプション取引などのFXの延長線上の新しい取引形態であるデリバティブも個人向けに提供されるようになりました。
信託受益権
信託受益権販売業は、信託業法の平成16年の施行により、金融機関以外の者が信託会社として信託業を営むことが可能になるとともに、信託契約代理店制度及び信託受益権販売業者制度が創設されたことに伴う登録制度です。
不動産信託受益権の売買、売買の媒介、私募の取扱い等を扱う事業者は、第二種金融商品取引業者と位置付けられています。金融商品取引法の施行直後には、既存の宅建業者系の事業者を救済する意味もあり、金融商品取引業や登録金融機関業務の未経験者であっても、所定の民間講習を受けることで、人的構成を満たすことができ、比較的緩やかな要件で第二種金融商品取引業に登録できていた時期もありました。
しかしながら、現在では、金融商品取引業や登録金融機関業務の未経験者のみで構成された不動産関連事業者が第二種金融商品取引業に登録することはほぼ不可能です。
不動産信託受益権関連業務であっても、金融商品取引業者ですので、登録には複数の金融商品取引業者又は登録金融機関での職務経験者が求められるようになっています。
なお、不動産信託受益権を原資産としたGKTKに係る売買等業務も、登録要件上はこうした不動産信託受益権関連業務を行うものとほぼ同等に位置づけられていますので、登録の際は登録要件の充足に配意する必要があります。
資産運用ビジネス
もともと、資産運用ビジネスは、投資信託と投資一任がメジャーな業態でした。
投信信託は、我が国の資産運用ビジネスの根幹というべき業態であって、投信委託業の制度の下、1961年には投資信託の残高が1兆円を突破するなど、高度経済成長期から大きく伸びた業態です。
他方、投資顧問業法に基づく投資一任(通称「一任勘定」)も早期に立ち上がった業態で、ファントラ・特金等の信託の形式を利用して、当該信託を投資一任契約に基づき運用するいわゆる投資顧問付き特金等もバブル期には広く利用されていました。
また、昭和60年前後から、投資事業組合(民法上の組合)がファンド・ヴィークルに利用されるようになりました。平成10年には中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律が成立し、いわゆるLPSの制度が創設されました。
他方、平成10年代に近未来通信事件・平成電電詐欺事件もありましたが、規制当局は十分な監督機能を発揮することができず、いわゆる匿名組合ヴィークルの問題も明らかになってきました。
総じて「組合型」の資産運用ビジネスは、金融規制外がその原則で、旧投資顧問業法における投資顧問業(一任)の概念では、十分に集団投資スキームの自己運用業務・自己募集業務は、許認可・登録の枠組みの下に置くことができませんでした。
平成16年にはみなし有価証券としてファンド持分の取扱業務を証券業に包接したり、あるいはファンド持分募集の募集を開示規制の下に置くなど、規制当局による必死の努力はありました。
とはいえ、金融商品取引法施行直前においても集団投資スキームの自己私募は登録・届出不要であり、既存の証券取引法及び投資顧問業法に基づく規制スキームではその限界が明らかでした。
金融商品取引法の成立
金融商品取引法は、こうした既存の証券業及び証券派生業の規制体系だった、証券取引法、金融先物取引法、投資顧問業法等の諸法令を統合して成立しました。
立法過程では、イギリスの投資サービス法を範として制定されたため、議論当初は投資サービス法(仮称)と呼称されていました(金融審議会金融分科会第一部会報告(平成17年12月22日))。
銀証分離とビッグバン
世界恐慌の反省を踏まえて制定されたグラス・スティーガル法(1933年銀行法)の考え方を継承して、我が国でも戦後長年に渡って銀証分離が行われてきました。
しかし、平成4年金融制度改革関連法による相互参入の解禁や、平成8年11月橋本総理が提唱した日本版の金融ビッグバン構想に基づく、平成10年の投信窓販解禁など、銀証分離の緩和が進みました。現在では、銀行や協同組織金融機関等は、金融商品取引業の一部について、登録金融機関として登録を受ければ、登録金融機関業務として行うことができることになっています。
銀証分離に限らず、金融ビッグバン時代は、規制緩和と金融市場の開放が広く実施されました。90年代、いわゆるウインブルドン方式として、東京市場では外資系金融機関が持て囃され、旧大蔵省も外資系金融機関の誘致を積極的に行っていました。当時を知る金融マンに聞くと、平成11年(1999年)に行われた某外資系銀行東京支店の銀行免許取消処分やプリンストン債事件まで、外資系金融機関への厳格な監督はほとんど行われていなかったという声もあります。
もっとも、現代では、とくにホールセールの金融規制分野においては、銀証シームレスな規制監督が行われています。内外差異は、業態特性に着目したモニタリングの差はあれども、規制上の緩急の差としては意識することはありません。
とはいえ、規制監督のスタンスを見る限り、総論として、銀行の監督が性善説に基づき、証券の監督が性悪説に基づくものであることは事実です。
金融商品取引業種別各論
金融商品取引法は、前述のように複数の業態を金融商品取引業として1つにまとめ、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の4種別をその骨格としました。以下にそれぞれの登録種別の概略を述べていきます。また、詳細に関してはリンク先の記事をあわせてご参照ください。
第一種金融商品取引業
第一種金融商品取引業は、旧証券取引法の証券業と、旧金融先物取引法の金融先物取引業を融合させた業態です。業務内容としては、株式や社債などのいわゆる1項有価証券の取扱い業務(証券業)、店頭デリバティブ取引業務(FX・証券CFD・暗号資産デリバティブ業務等)、その行う一定の業務に関して顧客から金銭や証券若しくは証書又は電子記録移転権利の預託を受けること(有価証券等管理業務)等から成り立っています。また、これらの他に、引受業務や、認可制のPTS等も第一種金融商品取引業に位置付けられています。
さらに令和元年金融商品取引法改正で、従来は集団投資スキームとして第二種金融商品取引業で取扱いが可能であった電子記録移転権利(セキュリティトークン)に関しても、その取扱い業務を実施するには第一種金融商品取引業の登録が求められるようになりました。
第二種金融商品取引業
第二種金融商品取引業は、主に、集団投資スキーム持分や信託受益権などの流動性の低い有価証券、すなわち株や社債等のメジャーな有価証券以外の金融商品取引法第2条第2項に定めるみなし有価証券を販売する業務です。また、みなし有価証券以外に投信委託受益証券等の一定の有価証券の自己募集や通貨関連市場デリバティブ取引も第二種金融商品取引業となります。
登録されている第二種金融商品取引業者の業務内容は、ファンドの募集又は私募(自己募集)及び募集又は私募の取扱いと、不動産信託受益権の売買、媒介又は私募の取扱い業務を行う業態がほとんどです。特定有価証券等管理行為や特定引受行為など、本来は第一種金融商品取引業に該当する一定の行為に関しては、第二種金融商品取引業者であれば一定の条件の下に行うことが許されています。
また、適格投資家向け投資運用業者が運用を行う投資信託や投資法人に係る受益証券・投資証券等の募集又は私募の取扱業務に関しては、本来は第一種金融商品取引業に該当するところ、いわゆるみなし第二種金融商品取引業として、第二種金融商品取引業の登録を受ければ行うことができるという緩和的規制が設けられています。
投資運用業
投資運用業は、投資一任業務(12号ロ)、ファンド運用業(15号)、投資信託委託業(14号)、投資法人資産運用業(12号イ)の業態から成り立つ業務種別であり、有価証券又はデリバティブ取引で権利者の財産を運用する業務です。投資信託の運用や、投資一任契約の締結、REITの運用等が代表的な業務です。
あくまで資産運用に特化した業務種別ですので、集団投資スキームの販売(募集又は私募及び募集又は私募の取扱い)又は自らを委託者とする投資信託受益証券の募集又は私募を行うには、第二種金融商品取引業の登録が必要です。また、自らが投資一任契約に基づき運用する投資信託受益証券の販売は、募集又は私募の取扱いに該当して、第一種金融商品取引業が必要になります。投資信託の運用を行う投資運用業者は、多くの場合、販売を担当する証券会社と連携してセールスにあたります。
投資助言・代理業
投資助言・代理業は、投資助言業務(11号)及び代理又は媒介業務(13号)から成り立つ業務です。投資助言業務は、投資顧問業務とも呼称され、旧法の投資顧問業(助言)を引き継ぐ制度です。株式に関する情報配信やシグナル配信、自動売買(EA)など、比較的中小業者が多く社数も多い業態です。
代理又は媒介に係る業務は、具体的には「投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介」です。既存の投資助言・代理業者の投資顧問契約の仲介及び投資一任契約の締結の仲介業務にあたります。投資助言業務に比較すると少数派であり、投資助言・代理業者のうち、媒介を行う業者は全体のせいぜい1、2割程度ではないかと思われます。
その他
有価証券関連業
金融商品取引法において、旧証券取引法の証券業の概念は、有価証券関連業に引き継がれています。有価証券関連業は、有価証券の売買又はその媒介、有価証券の取次ぎ若しくは代理、有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理、有価証券関連デリバティブ取引、有価証券の引受け、有価証券の売出し、有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い等が主要な業務であり、かつての証券業の範囲と非常に近似しています。
金融商品取引業者のうち、金融商品取引法の施行時に旧証券取引法第28条の登録を受けている者(みなし登録第一種業者)及び金融商品取引法施行後に有価証券関連業を行う者は、その商号中に「証券」という文字を使用することができるとされています。旧法では、証券と名乗ることが義務でしたが、金融商品取引法制下では、証券を商号に用いることは義務ではありません。
一般に証券業を引き継いだと考えられている第一種金融商品取引業と有価証券関連業はイコールに近いのかというと、そうでもありません。
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いは、いわゆるブローカー業務であり、対象がみなし有価証券の場合には第一種金融商品取引業者ではなく、第二種金融商品取引業に位置付けられます。実際、取扱い業務を行う第二種金融商品取引業者は、登録申請書の有価証券関連業の欄に〇を付して登録申請をすることになっており、第二種金融商品取引業者も広く有価証券関連業を行っています。
いささか旧聞に属する話ではありますが、証券取引法下では、匿名組合等の組合の持分の自己募集は業登録を要しなかったものの、匿名組合関係のトラブルが続いたことを契機に、平成10年代の法改正で、匿名組合等の組合型ファンドの持分の取扱いに限って、証券業に位置付けられていました。そのため、対象がみなし有価証券であっても、取扱い業務は有価証券関連業であるという整理は論理的に違和感がありません。
そうなると、理論上は、第二種金融商品取引業者でも「証券」と名乗ることができるのではないかと考えられます。知る限り実例が僅かに存在しています。ただし、新規に第二種金融商品取引業者として登録を希望する業者が「証券」の商号をつけるのは不可能であると解されます。
他方で、第一種金融商品取引業者でも通貨関連店頭デリバティブ取引を行ういわゆるFX業者は、有価証券関連業を行う者には該当しません。そのため、FX等の金融先物取引専業業者は商号に「証券」と名乗ることはできず、また、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者と異なり、適格機関投資家の要件に該当しないことから、FX業者は当然には適格機関投資家等特例業務を行う際の適格機関投資家になることはできないといった実務上の違いが出てきます。
平成20年前後、それを知らず、外国為替証拠金取引専業の某FX業者が誤って商号に「証券」と付けて変更登記を行い、財務局に注意を受けて商号をすぐにもとに戻した事例があったように記憶しています。
電子募集取扱業務
オンライン上で一定の非上場の一定の有価証券を取扱い(代理販売)する場合には、電子募集取扱業務の登録が必要になります。
さらに、こうした有価証券の取得申込をオンラインで受け付けする場合には、電子申込型電子募集取扱業務に該当します。その場合、本則となる第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業に併せて、電子申込型電子募集取扱業務として登録を受けることになります。
ただし、第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額電子募集取扱業務に該当する場合には、同業の登録を受けることにより、特例として、一定の少額の募集の場合に限り、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業の登録をせずに有価証券の取扱いを行うことができます。
第一種少額電子募集取扱業務は主に非上場株式の取扱いを中心に利用されています。これに対して、第二種少額電子募集取扱業務は事実上、制度として利用されていません。
適格投資家向け投資運用業
投資運用業のなかの特例として、前述のように適格投資家向け投資運用業の制度があります。適格投資家とは、金融商品取引法の定めるプロ投資家制度のひとつです。特定投資家、適格機関投資家、適格機関投資家等、特例業務対象投資家等の他のプロ制度とは異なっていますが、概ね適格機関投資家等の概念と一致しています。
適格機関投資家等特例業務届出者と違って、正規の登録業者ですので、いわゆるファンド業務だけではなく、投信委託業や投資一任業務等の業務も行うことができます。なお、運用資産額の上限は200億円とされていますが、これは適格機関投資家等特例業務の運用財産と合算になります。
適格機関投資家等特例業務
組合型ファンドの自己私募(7号)、集団投資スキームの運用業務(15号)に関して、少人数プロ向けに展開する場合には、適格機関投資家等特例業務の届出により、金融商品取引業登録なしで行うことができます。
適格機関投資家等とは、適格投資家及び特例業務対象投資家から構成されます。適格機関投資家等特例業務のファンドの成立要件は、適格投資家1名以上及び特例業務対象投資家49名以下で構成されていることです。
この49名は、よく株式、社債等の1項有価証券の私募の49名と混同されますが、適格機関投資家等特例業務の特例業務対象投資家の49名制限は、私募・公募の差異とは無関係です。適格機関投資家等特例業務は、私募が要件ではありますが、集団投資スキームの私募は実際の取得者499名までです。
そのため、1ファンドあたり最大で、適格機関投資家450名、特例業務対象投資家49名合計499名から構成された、出資者総数で49名を超える組成も可能です。
海外投資家等特例業務及び移行期間特例業務
令和3年金融商品取引法改正により、組合型ファンドの自己私募・募集(7号)、集団投資スキームの運用業務(15号)は、国内に設ける営業所又は事務所で、主として非居住者からの出資又は拠出を受けて運用を行う場合には、海外投資家等特例業務の届出により、金融商品取引業登録なしで行うことができるようになりました。
また、5年間の時限措置として、移行期間特例業務の制度が制定されています。
移行期間特例業務の届出を行えば、外国投資運用業者は、国内に設ける営業所又は事務所で、投資一任業務、投信委託業務、外国集団投資スキームのファンド運用業務及び政令に定める業務(第5項第1号)並びに投資一任業務を行う外国投資信託受益証券、外国投資証券及び外国集団投資スキームの募集又は私募の取扱い、自らを委託者とする外国投資信託受益証券の募集又は私募、自らを発行者とする外国集団投資スキームの募集又は私募を行うことができます。
コロナ禍の国際間の往来の減少もあり、海外投資家等特例業務は令和4年まで届出事例がありませんでした。そのため、第二種少額電子募集取扱業務等と同じく「利用されない制度」となっていましたが令和5年3月31日付で初の届出者が出ました。