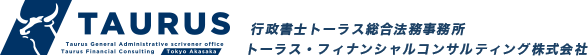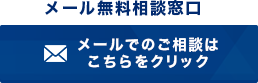ファンド組成について
 このページの目次
このページの目次
ファンドの種類-組合型ファンド-投資信託型ファンド-会社型ファンド-当事務所のファンド組成支援-どんな手続きが必要なのか-どのくらいの期間がかかるのか-どのくらいの費用がかかるのか
ひとくちに「ファンド」といっても、その法的な形態は集団投資スキーム(組合・パートナーシップ等)、投資信託、会社型(投資法人・TMK等)など様々です。
「ファンド」という言葉は、法令上の正式な言葉として存在しません。そのため、まずは組成希望者が具体的に何をしたいのかを伺って、最適なスキームを選択する必要があります。
本ページではファンドの組成・設立をお考えの金融法人及び金融関係事業の開業を検討されている方を対象に、ファンドの概念と、当事務所でのサポート内容について主にご説明させて頂きます。
ファンドの種類
一口に「ファンド」といっても、その商品性には大きく分けて、組合型ファンド、投資信託型ファンド、会社型ファンドの3種類があります。
また、その組成・販売・運用にあたってのライセンスも、第二種金融商品取引業、第二種金融商品取引業及び投資運用業、不動産特定共同事業許可及び商品投資顧問業許可など、内容と商品性によっていろいろと変わります。
以下、ケース別に、必要なライセンス・ライセンス取得までの期間・費用感について案内していきます。それぞれのライセンスの詳細に関しては、随時リンク先をご参照ください。
| 分類 | 代表的形態 |
| 組合型ファンド | 有限責任事業組合(LLP) |
| 投資事業有限責任組合(LPS) | |
| 民法組合(NK) | |
| 匿名組合(TK) 外国法の組合等 |
|
| 投資信託型ファンド | 投資信託 |
| 外国投資信託 | |
| 会社型ファンド | 投資法人 |
| 特定目的会社(TMK) | |
| オフショア法人等 |
組合型ファンド
主として有価証券又はデリバティブ取引を行うファンド
関東財務局のファンド事業にかかる登録の要否で言及されている「ファンド」とは、この組合型のファンドのことです。組合型ファンドは「集団投資スキーム」とも呼称されます。
小規模~中規模のサイズで、主として上場・未上場株式、債券、日経平均先物やFX等の投資性のある金融商品(有価証券又はデリバティブ取引)に投資するファンドを組成する場合は、匿名組合や投資事業有限責任組合等の組合型の契約を利用するのが、一般的だと思います。
その際には、第二種金融商品取引業及び投資運用業の登録をする方法と、少人数のプロ向けに適格機関投資家等特例業務に基づいて組成する方法があります。
第二種金融商品取引業及び投資運用業の登録は、1年以上の期間がかかり、従業員も経験者5~6人は必要になります。また、ライセンス費用も数百万~と相当の額になりますが、一般投資家向けに広く勧誘できます。一方、適格機関投資家等特例業務であれば、1~2か月程度の期間と、数十万の程度の費用に留まり、従業員数の要件もありません。しかしながら、出資可能な投資家は少人数のプロのみに限定されます。
事業型ファンド
主として有価証券又はデリバティブ取引に投資するファンドではなく、再生可能エネルギー・ファクタリング・船舶航空機・その他現物投資のファンド(事業型ファンド)については、匿名組合の形態で組成するのが一般的で、その勧誘には第二種金融商品取引業の登録が必要になります。第二種金融商品取引業の登録は、最低でも経験者4名程度が必要です。
ちなみに、一般的な事業会社の運転資金や資金調達を目的として自社のためのファンドを組成したいという検討は、いわば「工場の資金繰りが苦しいから銀行を作りたい」と同種の話に近く、現実的ではありません。
その他ファンド種別
なお、現物不動産ファンドは、これらとは別の規制に服します。また、その他に貸付型ファンドの組成には貸金業、コモディティファンドの組成には商品投資顧問業の許可等、運用の内容により必要な許認可は変わります。
経験者のスタッフを確保できない状態で、プロ投資家向けではなく一般投資家向けの組合型ファンドを組成・販売することは不可能です。そうした場合には、会社型ファンドの形態を検討することになります。
「投資クラブ」スキームであれば、組合形態でも金融商品取引業登録が不要なのではないかという質問をいただくことがありますが、投資クラブスキームは旧証券取引法時代の制度です。現在の金融商品取引法では集団投資スキーム規制に抵触する可能性が高く、使えません(※)。
※平成19年パブリックコメント(P9 No.30・P16 No.59/60)への金融庁回答「金商法の下では、投資クラブのメンバー全員が出資対象事業に関与する場合(金商法第2条第2項第5号イ、金商法施行令第1条の3の2)には、その持分は有価証券とみなされる「集団投資スキーム持分」に該当しないものと考えられますが、個別の投資クラブが当該要件を満たしているかどうかは、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断されるべきものと考えられます。」
投資信託型ファンド
投資家資金を投資信託型の形態で出資を受け販売する場合には、運用に投資運用業(投信委託業又は投資委託業者に対する投資一任業)が必要になります。また、その投資信託受益証券の勧誘には、代理販売(取扱)の場合、第一種金融商品取引業、直販の場合には第二種金融商品取引業の登録が必要になります。
第二種金融商品取引業及び投資運用業の登録は、1年以上の期間がかかり、従業員も経験者5~6人は必要になります。また、第一種金融商品取引業の登録も同じくらいの態勢感が必要になります。ライセンス取得に要する費用も通常は数百万からと相当の額になります。
ただし、適格投資家向け投資運用業に該当する場合には、自ら投資一任契約に基づき運用する投資信託の取扱いの場合、第一種金融商品取引業ではなく第二種金融商品取引業とみなすという規定があり、第二種金融商品取引業登録があれば、当該投資信託受益証券の取扱いが可能です。
なお、一昔前には、ケイマン、シンガポールや香港等に外国籍の投資信託を組成し、国内の金融商品取引業者が、投資助言契約又は投資一任契約に基づき外国籍投資信託を運用するとともに、国内では販社となる証券会社(第一種金融商品取引業)に私募の取扱を依頼するスキーム(いわゆる「外投私募」)を多く見ました。
しかし、平成24年には投資助言契約でヘッジファンドのハンドリングを行っていた、投資助言・代理業者の登録が取消されるなど、かかるスキーム採用には投資運用業又は独立した現地の実態ある運用会社が必要であることが明らかになっています。
一世を風靡した業態ではありますが、近年ではスキームの多様化を受けて、外投私募スキームの選択率は以前よりも低下している印象です。
会社型ファンド
会社型ファンドには、投資法人の形態、特定目的会社を利用する方法(TMK)及び一般的な法人を便宜的に投資ヴィークルとして利用する形態(SPC)の3種類があります。
投資法人の形態の場合には、投信・投資法人法に基づく投資法人として設立することになります。その勧誘は第一種金融商品取引業、運用には投資運用業の登録が必要になります。いわゆるREITはこの形態です。投資運用業の登録は、1年以上の期間がかかり、従業員も経験者5~6人は必要になります。また、第一種金融商品取引業の登録も同じくらいの態勢感が必要になります。ライセンス費用も数百万からと相当の額になります
特定目的会社は、不動産等の資産を流動化する際に利用される、資産流動化法に基づく特別な法人形態です。主に、不動産証券化のために利用されます。通称TMKと呼称されます。
一方で、一般的な法人を投資ヴィークルとする場合、社債、オフショア法人株式等が利用されます。こうした形態のファンドの募集は、自社の役職員で募集する限りは、私募制限等を守れば、特に許認可・登録を要しないので、最も組成に向けたハードルが低い形態です。期間も1~2か月程度、費用も数十万円からと低額です。
なお、オフショア法人株式には、内国源泉所得の法人税課税やタックスヘイブン対策税制等の問題がありますので、国外に人員が常駐する拠点がないスキームには利用できません。
また、近年ではブロックチェーン化された一定の持分会社の社員権の自己私募及び募集が第二種金融商品取引業に位置付けられるようになりました。また、持分会社の社員権の自己私募及び募集は、金融商品取引業登録なしの従業員が原則としてこれを行うことができなくなるなど、総じて規制強化のトレンドにあります。
以上、規制の概略をざっと説明してきましたが、これだけで全容を説明しきれているわけではありませんし、概論なので、実際の規制はより入り組んでいます。詳細に関しては、リンク先のコンテンツを読んでいただくか、是非お電話・メール等にてお気軽に当事務所までお問い合わせください。
当事務所のファンド組成支援
当事務所は、証券・金融関連業務専門事務所としての高い専門性と、組織としての確実な事務処理によりお客様の資産運用ビジネスを支援しております。
集団投資スキーム型のファンドはもちろんのこと、投信委託業の登録や、外国籍投資信託の私募手続(ファンド登録)を含む投資信託型ファンドの展開も支援可能であり、資産運用ビジネスに幅広く支援実績があります。
また、当事務所は、ケイマン・ラブアン・BVI等のオフショア・スキームを含む複雑なクロスボーダー・ファンド組成も大手法律事務所と連携しての多数の実績があります。監督官庁の方針や業界の方向性を常に情報収集しており、規制動向に関しても的確なアドバイスが可能です。
どんな手続きが必要なのか
上記の通り、ファンドの種別により異なりますが、一般投資家向けに組合型のファンド販売する場合には第二種金融商品取引業及び投資運用業が必要になるのが原則です。ただし、少人数プロ向けファンドの場合には、適格機関投資家等特例業務で届出のみでファンドを組成することができます。
また、会社型ファンドの場合には特段の行政手続きが不要になるケースが多いです。また、投資信託の形式の場合には、運用に投資運用業、販売に第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業が必要になります。
どのくらいの期間がかかるのか
組合の種別、ライセンス、想定する投資家層により大きく変わってきます。詳細は、上記のファンドの種別の項目にそれぞれ記載しています。総じて、金融商品取引業登録をする場合には、長くかかかる傾向があります。機関投資家向けの場合には半年程度で開業する余地があり、一般投資家向けの場合には1年以上と、より長く手続き期間がかかる傾向があります。
これに対して、金融商品取引業登録を行わない適格機関投資家等特例業務等や会社型ファンドのスキームの場合には、1~2か月程度で組成完了することも可能になってきます。
どのくらいの費用がかかるのか
案件によりけりですが、一般論として最低50万円程度からと考えられます。
一般的なファンド組成では弁護士費用等込みで200万円程度が一つの業界的な目安といえますが、当事務所では内容によりこれよりは低い費用感で対応が可能です。
一方で、第二種金融商品取引業や投資運用業などの金融商品取引業登録手続きが伴う場合には、かかる費用は数百万円とより高額になります。他方、10万円、20万円といった予算感では、「金融ゴッコ」を超えるマトモなファンド商品を組成するのは難しいと考えられます。
なお、世間には出資総額で200万、500万又は1000万レベルのマイクロ出資対象事業が存在するのも事実です。こうしたマイクロ事業は、投資型クラウドファンディングを除き金融商品取引法の規制レベルに馴染みませんし、金融商品取引法対応を前提とする報酬体系にも合致しません。
こちらにも書きましたが、ファンド設立のような仰々しいことはせず、少人数の身内や内々からの借入金としての法的整理で事業を行うのが現実的な選択肢です。