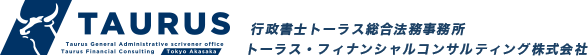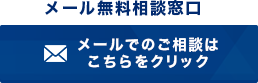このページの目次
このページの目次
戦後の株式市場-太平洋戦争と株式市場-ポツダム宣言-GHQとアプレゲール-ドッヂライン-光クラブ-特需景気とスターリン暴落-神武景気-証券ブームの時代-株が上らなかった60年代-株屋の時代-証券市場の拡大-幻想の経済成長モデル-電子立国神話-資本市場の開放と自由化-破滅の予感-バランスシート-ジャパン・アズ・ナンバーワン-運命のバブル崩壊
証券業界の歴史を知る
戦後の株式市場
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者は、かつて証券取引法に基づく証券会社として規制されていました。
証券取引法は1948年制定の法律であり、金融商品取引法が施行される2007年まで、証券業界は「証券会社」が中核となっていました。
証券取引法に基づく「証券会社」の時代には、戦後の取引再開、朝鮮戦争の上昇相場、スターリン暴落、高度経済成長、オイルショック、円高不況、平成バブル景気を経てバブル崩壊後の冬の時代まで、様々な局面がありました。
太平洋戦争と株式市場
真珠湾攻撃にはじまる太平洋戦争の開戦は、株式市場にとってプラスの材料でした。
戦時中の日経平均株価は、真珠湾攻撃の翌日の株価急騰から始まって、1942年12月の「連合艦隊最期の勝利」といわれる南太平洋海戦頃まで継続的に上昇しました。
世に言う「南海決戦場」であるラバウルの制空権争いや、ガダルカナルで日米の死闘が続いた1943年末まで堅調を維持するものの、飛び石作戦が始まって、マキン、タラワが陥落し、絶対国防圏が怪しくなった1944年に入ると株価は急落しています。
しかしながら、同年6月のサイパン陥落を株価の底として、国による無制限の株式の買い支えにより株価は上昇基調に転じ、1945年の夏に至っては、繊維などのいわゆる平和株に上昇局面がみられています。
ちなみに、1944年10月の台湾沖航空戦において、大本営が、長井雷撃隊をはじめとした精強なT攻撃部隊の現地報告を信じて虚偽の大戦果を発表したことで、真に受けたニューヨーク株式市場が暴落したことは、未だに証券市場の語り草になっています。
なお当時は、いわゆる「大本営発表」により、本当の戦況は国民に伏せられていたと理解するのが一般的ですが、それは地方や子供に限った話で、都会では実際にはそうでもなかったようです。
当時を知る証券マンに、直接聞いたことがありますが、当時の商業の中心だった大阪の船場ではミッドウェー海戦の敗北は市民にほぼリアルタイムで伝わっていたそうです。また、終戦時の玉音放送では、大人たちが、「よっしゃ明日から空襲がなくなるで」と皆で大喜びしたと聞いたことがあります。
人間は、今も昔もそう愚かではないということでしょう。
ポツダム宣言
昭和20年8月14日のポツダム宣言受諾と、15日の敗戦を目前にして、大本営の幕僚であった海軍の中島中佐は「我々の知らないところで、何か重大なことが討議されているらしい。東京株式取引所の日報を分析してみると、7月下旬以来ぢり高歩調をたどっていた鐘淵工業日清紡などの所謂平和株が8月に入って一段高になり、日清紡は昨日106円ちょうどの高値を付けた。而も、東株は本日9日の立ち合いを以て取引を当分停止するそうだ。これは何か国策上の大変化が起こる前兆と考えざるを得ない。」と会議で発言しています。
中島中佐は慧眼でしたが、結果的に陸軍も海軍も敗戦で解体することになります。
広島・長崎への原子爆弾投下により停止された市場は、その後1949年の再開されるまで、3年9か月の長きに渡って閉鎖されることになりました。
GHQとアプレゲール
戦後、GHQは取引所の再開を禁止。しかしながら、東京証券取引所のあった兜町や大阪証券取引所のあった北浜では、公園や路上に証券業者が集まって、半ば組織的な集団売買が開始されました。正式に証券取引所が再開されるまでの間、こうした非公式な取引が、事実上証券流通を担っていたとされています。
GHQは、1949年に証券取引所再開にあたっての条件である証券取引所三原則を発表。上場銘柄の取引は取引所で会員により行われること,取引所での取引はその順序に従い時間的に記録されること,先物取引の禁止の原則が示されました。
これを受け、1948年制定の新たな証券取引法の下、1949年5月16日、東京証券取引所と大阪証券取引所で、立ち合いが再開されました。
ドッヂライン
再開の時期は株式市場にとって、決していいタイミングではありませんでした。
1949年2月に、GHQ経済顧問であるデトロイト銀行頭取のジョゼフ・ドッジ博士が勧告したドッラインが採用され、日本経済は戦後の竹馬経済によるハイパーインフレの時代を終えてデフレ不況に突入。同年11月には13営業日続落を記録。翌年の1950年7月6日には、日経平均株価は歴代最安値となる85.25円を記録しています。
ちなみに、1949年11月24日には、この暴落を完全に予見し、大規模な空売りを仕掛けていた光クラブ山崎晃嗣氏が、惜しくもタイミングの僅かなズレが原因で亡くなられています。とはいえ同氏の天才的な慧眼は今も語り継がれています。
この時期は証券取引所の制度上、空売りが出来なかったので、同氏がカラ売りしていたとの主張はおかしいと論難する向きがありますが、実際には空売りが可能であったのは、同氏の著作を読めばわかります。
光クラブ
時代が変われば法令も常識も変わります。
山崎晃嗣氏が運営していた光クラブの事業モデルは、戦後の金融業取締規則の失効及びマル公(物価統制令)の有名無実化を背景としたスキームでした。
ドッジラインの資金詰まりによる高金利ファイナンスへの社会的な需要を考えれば、現代人の視点からは、光クラブへの論難の法的構成は枝葉末節な微罪です。
本件では銀行法違反と物価統制令違反が問題になりましたが、光クラブのスキームが銀行業に該当するとする法的構成は相当に無理があります。元本保証を禁ずる出資法が存在しなかった当時ですので、現在に置き換えればソーシャルレンディング業者に銀行業の免許を求めるのと法的に同一の構成です。
さらに、仮に法令違反だとしても当時の銀行法違反の罰金は50円でした。1948年当時の物価は現在の100分の1程度ですので、現在の感覚では罰金5000円です。
現在5万円以下の罰金が定められている自転車の傘さし運転やブレーキの利かない自転車の運転の、さらに10分の1の罪となります。
また、同じく逮捕容疑とされた高金利処罰の物価統制令違反は、同業の森脇氏が直近で一審で無罪とされていました。下級審とはいえ、判例上適法とされている事案は適法と考えるのが普通です。よって、現代では、光クラブは実際には概ね適法でかつ持続性がある業態であったと考える意見が多いです。
特需景気とスターリン暴落
朝鮮戦争により息を吹き返したとされる日本経済ですが、株式市場もまた朝鮮戦争により復活しました。53年2月4日には日経平均株価は474.43円まで上昇。1950年の安値から5倍以上の上昇になっています。
しかしながら、1953年3月5日に当時のソビエト連邦の最高指導者であったヨシフ・スターリンが死去したことにより、東西の緊張緩和、朝鮮戦争の終結を見越して軍需銘柄を中心として株式市場は暴落。当日の日経平均株価は、前日比37円80銭安344円41銭となり、日経平均株価の下落率は実に10%となりました。
朝鮮戦争の終結後は日本経済の先行きを悲観する声が大勢であったとされています。
時代の停滞感を反映してか、1950年の日大ギャング事件や前述の光クラブ事件と並んで、いわゆる「アプレゲール」犯罪の典型とされている、慶應卒の元証券マンによるバー・メッカ殺人事件も、1953年7月に発生しています。
神武景気
こうした悲観的な予想に反して日本経済は、1954年12月から神武景気に突入。1955年からはいわゆる高度経済成長期とされる時代に突入します。
1955年の日経平均株価は、大発会の369円45銭に始まって大納会425円69銭へと上昇。1956年に549円14銭、1957年は474円55銭に留まるものの、1959年には666円54銭、1959年に874円88銭、60年には1356円71銭まで上昇しています。
証券ブームの時代
こうした1950年代のスターリン暴落後の力強い相場もあり、高度経済成長期には、株式市場はひたすら上昇が続いたのではないかという漠然としたイメージがあります。
実際、1957年6月まで続いた神武景気後に訪れた、1957年から1958年にかけての「なべ底不況」は、上記のように短期間で克服され、いわゆる「岩戸景気」を経て、1961年には投資信託の残高が1兆円を突破しました。
「銀行よさようなら、証券よこんにちは」のキャッチフレーズが流行語になったことは、証券業界では現代も語り継がれています。
私が金融業界で働き始めた当時、相談役クラスには高度成長期を経験した証券マンが残っていて、高度成長期にはボーナスが年12か月支給されたと聞いたことがあります。好景気であれば株式が上昇するということが当たり前の感覚である我々現代人にとって、高度成長期の株式市場はあたかも桃源郷のような状況だったのではないかと思われるところです。
しかし、日経平均株価の推移を超長期で眺めると、異なった事実が分かります。高度成長期真っ只中のはずの1960年代、日経平均株価はほとんど上がらなかったのです。
株が上がらなかった60年代
日経平均株価が大きく上昇したのは、主に1958年-1961年、1968年-1973年、1983-1989年で、特定の時期に強く偏っています。例えば1961年7月14日に1822.02円だった日経平均株価は、1968年1月4日には1266.27円とむしろ下落しており、1961年の水準を回復するのに1969年まで要しています。

高度経済成長期真っ只中である1960年代、実は日経平均株価はほぼ横ばい状態であったという事実は、現代人の眼から見ると衝撃的です。実際、1957年頃まで業界首位であった山一證券は、東京五輪と東海道新幹線の全通の翌年である1965年、証券市場の低迷を原因とした経営難に陥って田中角栄蔵相による日銀特融により救済される騒ぎになっています。いわゆるオリンピック不況です。
また、社員に東大卒を多く集めて「法人の山一」と称されていた山一證券に比べ、この時期、業界トップに立った野村證券は、いわゆる「どぶ板営業」でリテール顧客を開拓して、足腰の極めて強い経営体質を築きあげていたことは、後年のバブル崩壊後の明暗を分ける形になりました。
株屋の時代
大正昭和の証券業界は、今よりもずっと投機色が強く、証券会社は「株屋」と呼ばれて、経済界での地位は今よりもずっと低かったとされます。さらに遡れば、昭和10年に山一證券第三代社長に就任した太田収氏が入社した日露戦争の時期には、東大卒で証券会社に入社する者は皆無であったと記録されています。
こうした理由の一端は、戦前から戦後のある時期までの金融システムは、銀行を中心として構築されていたことです。
戦前はもちろんのこと、戦後も直接金融主体の時代は長く続きました。興銀(IBJ)や、これに続く長銀(LTCB)を頂点とした長期信用銀行や、戦前に存在した横浜正金銀行を継承する外為特化型の銀行だった東銀(BOT)、第一勧銀(DKB)、住銀、富士銀等の都銀の行員は名実ともに同世代の選良でした。
また、外資系銀行ではJP・モルガンが頭一つ抜けた存在だったとされます。
こうした風潮の下においては、ぐっと現代に近いバブル前の80年代ですら、東大・京大卒で証券会社に就職する者は少数派だったと伝わります。
まさに隔世の感がありますが、かつての直接金融重視の時代の背景には、現代に比較し、日本経済での株式市場のプレゼンスがずっと小さかったこと、それがゆえに株式相場の不安定性、不確実性が現代よりも強かったこともあると思われます。
証券市場の拡大
これは数字の上でも証明されており、東京証券取引所の統計データでは、1967年大納会の東京証券取引所の時価総額は9兆2706億円。同年の日本のGDPは47兆5790億円と東京証券取引所の時価総額はGDPの約20%に過ぎません。
60年代の低迷を経た日経平均株価の急激な上昇は、列島改造論の頃に始まり、二度のオイルショックを乗り切ると、1983年頃から上げ足を急速に早めました。
1987年のNTT株上場は国民的熱狂を巻き起こし、ついに1989年大納会には日経平均株価が伝説ともいえる史上最高値38,915円に到達しました。この記録が2024年2月22日に破られるまでバブル高値は証券業界における伝説的株価であり続けました。
バブル期の1989年大納会の東京証券取引所の時価総額は611兆円。当時421兆1825億円だったGDPの約141%まで増加しています。
その後の証券市場は長い冬の時代を迎えたものの、大底であった2002年の大納会においても、東京証券取引所の時価総額は247兆円とGDPに対して約47%の水準を維持。
令和3年11月現在、東京証券取引所の時価総額は762兆円とバブル期を上回るとともに、GDPに対する比率も約145%となっています。
さらには、2024年2月22日に至っては日経平均株価は実に約34年ぶりに史上最高値を更新しています。これを見る限り、戦後史は、経済における証券業界の相対的な地位向上の歴史といっても過言ではないでしょう。
幻想の経済成長モデル
1955年から1973年の19年間を高度経済成長期と呼称しますが、実際には前期と後期でその経済成長は質的に異なっていたとされます。
漠然とした輸出大国のイメージに反して、高度経済成長期の国際収支は均衡状態であり、好況により工作機械の輸入が増加すると貿易赤字が増加する、いわゆる「国際収支の天井」が経済成長の制約要因になっていました。
この「国際収支の天井」問題は、1960年代の株式市場の低迷とも関連していて、昭和40年不況の始まりは、オリンピックの終了に伴う反動とする俗説に反し、実際には1961年7月以降、国際収支の赤字改善のため公定歩合が利上げされたことに始まるとされています。
日本が本格的な貿易黒字体質に転じたのは1970年代に入ってからですが、1974年及び1980年には二度のオイルショックもあって大幅な貿易赤字に陥るなどしています。貿易黒字が目だって増加したのは、データを見る限り明らかに1981年以降です。
戦後貿易摩擦の嚆矢となった日米繊維交渉が1955年に始まっていることから、誤解しやすいのですが、本格的な貿易黒字が始まったのは、実は高度経済成長がとっくに終わった後です。
高度経済成長は、封建以来の農村経済を産業資本主義に包接(インクルージョン)する過程であったという議論があります。これに対し、80年代から現代に至る株式市場の相対的なプレゼンスの増大と、市場国家化現象は、産業資本主義をグローバル資本市場に包接するための新たなインクルージョンの過程なのかもしれません。
電子立国神話
80年代の日米半導体交渉、90年代の日米自動車交渉を記憶する日本人は多いでしょう。また、1991年NHKスペシャル「電子立国日本の自叙伝」は、まさに世界の頂点に立った加工貿易国、ニッポンのある種の到達点を象徴するものです。
1995年、クリントン政権に立ち向かい、日米自動車交渉に臨む橋本龍太郎通産大臣の雄姿ははっきりと記憶に残っています。
しかしながらこうした「電子立国」「加工貿易」神話は、実は極めて歴史が浅く、日本の高度成長は、その末期近くまで内需主導でなされていた事実は記憶にとどめるべきであると思います。
80年代から90年代にかけ、輸出主導での高度成長は、日本を先頭とした雁行モデルと称され、NIEs、ASEAN諸国がこれに続きました。これらの諸国では、アジア通貨危機までの間、株式や不動産価格の急激な上昇が生じたことで、加工貿易による外貨獲得と株式市場の上昇こそが経済成長であるという漠然とした成長観が形成された感があります。しかし、実はこれは色濃く80年代の世相を反映したもので、韓国総合株価指数や台湾加権指数を見ても、60年70年代は相対的に上げ足が鈍く、急激な上昇は日本と同じく80年代後半に発生しています。
資本市場の開放と自由化
日本は、1964年に IMF8条国へ移行したことで、資本取引の自由化を公約。1967年以降、段階的な資本自由化措置が講じられました。これにより、1970年代には円建て外債や外国株式の国内販売も行われるようになり、1972年には外国証券会社に対して初の証券業免許が付与されました。
また、前述の日米貿易摩擦に起因して、アメリカは、金融、資本市場の自由化を妨げる規制の撤廃を要求しました。折しも80年代の新自由主義経済学の興隆で、レーガノミクス、サッチャリズムに倣い、我が国でも規制緩和の流れが強まりました。
もっとも、こうした資本市場の自由化は、上場企業の買収防衛策としての株式の持ち合いを促し、結果論になりますがバブル崩壊後の苦境への道が敷かれました。
破滅の予感
株式持ち合いにより浮動株比率が低くなったことで、株主権のうち共益権は空洞化。企業の経営規律が低下するとともに、いわゆるシャンシャン総会が理想とされ、80年代にはうるさい株主は総会屋に黙らせるという今にして思えばブラックジョークのような企業統治が行われていました。
証券会社は、こうした状況を看過するだけではなく、自らもまたこうした行為に手を染め、後の4大証券利益供与事件では当時の大手証券会社がいずれも総会屋に利益供与をしていたことが判明。世論の厳しい非難を受けました。
また、浮動株比率の低下は、株式の流動性の低下により株価の動きが極端になることを意味します。
これは、株式市場の鉄火場化を招き、株式市場は、仕手戦や財テクといったあたかもギャンブルの舞台の様相を呈するようになりました。「バブル期最後の戦い」として、現代も語り継がれる本州製紙の仕手戦は、証券市場の伝説になっています。
バランスシート
株式持ち合いにより上場企業が取引先や系列企業の株式を資産として大量に抱え込んだことで、株価の下落に弱い財務構造となったことも、いわゆるバランスシート不況の長期化の原因になりました。
バブル崩壊後に、証券会社が次々と苦境の陥ったのは、営業特金等で株式の損失補てん契約を顧客企業と結んでいたことが原因とされていますが、これも結局は企業が本来事業には必要のない株式を大量に抱え込んでいたことが究極の原因といえます。
バブル前の日本では、同様の構造が不動産にもありました。
こうして「鉄火場」化した株式市場が主導する株高はいつ崩れてもおかしくないといえます。こうした中で、ひとたび実際に資産価格の下落が始まれば、土地や株式を抱え込んでいる企業がバタバタ倒れるのは火を見るよりも明らかで、それに融資している銀行もまたただでは済まないことは、当然に予想されます。
究極的には、持ち合いと土地神話が、資産価格の下落が一気に経済システム全体を破壊する危険な経済構造を形成してしまったといえます。
ジャパン・アズ・ナンバーワン
1985年のプラザ合意をきっかけに円高不況に陥った日本経済を支えるため、日銀は長期間の金融緩和を維持。
1986年に4回、1987年に1回と相次いで公定歩合の引下げが実施され、2.5%の公定歩合は1989年5月の利上げまで2年3カ月に渡って維持されました。これにより生じた金余りで、株価、地価共に急激に上昇。1990年の日経平均株価の平均PERは約80倍に達しています。
バブル期には、財テクブームの流れに乗っていわゆる4大証券を中心として証券業界は膨大な利益を計上。この世の春を謳歌したとされます。
1989年の世界の企業の時価総額は1-7位までを日本企業が独占。1989年10月には、三菱地所がロックフェラーセンターを所有するロックフェラーグループの過半の株式を取得。山手線の内側の地価だけで米国全土が買えるとされていました。
運命のバブル崩壊
今にして思うと、1989年まで緩和政策を維持したことは正気ではないように感じられますが、政策担当者の証言では、円高不況を考慮すると早期利上げの選択肢は政治的に事実上不可能であって、どうすることもできなかったとされています。
1989年の大納会で38,915円の史上最高値を付けた日経平均株価は、1990年代に入って下落をはじめ、1992年8月には14,309円まで下落。
不動産価格も1992年には基準地価が初のマイナスに転じるなど、間接金融主体の金融システムにおいて、担保価値が急激に失われる信用収縮が進んでいました。
バブル崩壊が誰の目にも明らかになった重大な局面で、リクルート事件、佐川急便事件等で、政府与党の権力基盤が動揺していたことが日本経済の致命傷になりました。
1992年8月に当時の宮澤喜一首相が、銀行への公的資金注入を示唆するものの、銀行業界、大蔵省及び世論の激しい反発に遭い断念。1993年には宮澤おろしの果てに自民党が下野するに至ったことで、金融システムの早期安定化は実現できませんでした。
こうして日本経済は、泥沼の平成不況に突入していきます。