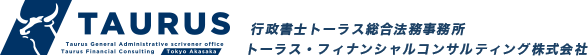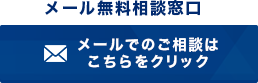金融商品取引業の無登録営業の罰則
 このページの目次
このページの目次
刑罰と行政処分等-どういうときに問題になるのか-表示自体も禁止-海外ライセンスもほぼ無意味-無登録営業の態様-民事的にも無効
※重要:当事務所は金融関係事業者向けです。
一般消費者・トレーダー・違法行為者等からの相談は受けません。
刑罰と行政処分
いわゆる金融商品取引業を、財務局の登録を受けずに無登録で営業した場合、罰則は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、となっています(金融商品取引法第197条の2)。また、法人・団体に対しては5億円以下の罰金が科されます(金融商品取引法第207条)。
いわゆるファンド的な利殖事案の検挙では、かつては出資法違反と詐欺罪の構成が主流でしたが、現代では警察が金融商品取引法違反でも立件する例が増えてきています。
また、無登録営業を行った際には、無登録で金融商品取引業を行うものとして、金融庁のホームページで公開されます。そうなると金融機関等の反社会的勢力のリストや信用情報機関のリストに「反社会的勢力」として登録されるとされています。
そのため、無登録営業で公表された場合には、法人の口座を強制閉鎖されたり、代表者の金融機関の個人口座も開設できなくなったりするのはもちろんのこと、住宅ローンを借りることもできなくなり、賃貸住宅すら審査で拒否されるようになります。よって、社会的には、暴力団同様とみなされ、経済活動から事実上排除されることになります。
賃貸住宅の審査に関しては、家賃保証会社による保証を受けない物件の場合には、大家の審査能力の限界により露見しない場合もあります。しかし、メジャーな家賃保証会社による審査がある物件では、現在では、融資並みの反社会的勢力該当性の審査が行われているため、金融庁・財務局からの登録取消等を受けている事業者及びその代表者等の場合には審査を通過するのは難しいようです。
無登録営業には、ファンド的な利殖事案もあれば、投資顧問・情報商材的な事案もあり、また、海外無登録FX/PAMM/MAMM等の国際的なものまで、いろいろな形態があります。また、令和3年から令和4年にかけては、SNSを利用して勧誘する国際ロマンス詐欺型のFXやバイナリーオプション取引の無登録営業も増加しています。
しかしながら、登録を受けないと行うことができない業務を行った場合、無登録営業で金融商品取引法違反を構成することは、いずれも共通です。
事案により、これに加えて詐欺罪、出資法違反、特定商取引法違反等の罪が付加される場合もあります。こうした事案が、どこまで立件されるのか、厳罰に付されるのかという質問を事業者から受けることがありますが、1-3割前後といった実感です。
出だし最初の数年は大丈夫でも、最終的には相応の割合で逮捕されますし、犯意がないまま詐欺の片棒を担いだ場合には民事で破産します。財務局も一定程度を超える被害額の事案は積極的に刑事告発しているそうですが、捜査当局もなかなかこうした告発を取り上げず、全件での事件化は出来ていないそうです。
いずれにせよ、家宅捜索から逮捕に至り、罰金、執行猶予はもちろん、実刑で服役している方も、無登録営業をする者には珍しくありません。新聞報道では、交通事故等と同じく、ごく断片的にしか報道されていないため、可視化されていないだけです。
問題は刑事だけではありません。ポンジスキームに手を貸して代理店だのエージェントだのをやってしまい、案件が破綻してから民事訴訟で負け、5年、10年、下手すれば15年も延々と民事の賠償金を払い続けている実例を散見します。
連絡を取れないようにして、逃げて賠償金を払わないのは簡単ですが、そこで逃げると、風評等の問題もあり、基本的には経済界では二度と表に出れません。腹を括って逃げるか、表社会に残るために払うかの二択になります。
禁止又は停止、公表、検査
金融商品取引法第192条には、無登録営業を行う者に対する裁判所の禁止又は停止命令が定められており、裁判所は、証券取引等監視委員会及び財務局の申し立てに基づき、無登録営業を行う事業者に対して、業務を禁止又は停止を命ずることができるとされています。また同第192条の2では、金融商品取引法違反行為を行った者の氏名等の公表処分に関して定めがあります。
さらに、同第187条では、無登録営業を行っている疑いがある事業者に対して、当局は、報告命令を発したり、業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査することが可能とされており、この条文に基づき、登録を受けている金融商品取引業者や適格機関投資家等特例業務届出者等をはじめとする登録・届出業者でなくとも、証券取引等監視委員会及び財務局の臨店検査が行われる場合があります。
どういうときに問題になるのか
無登録営業をしたとしても、お金を返していれば問題にならないのではないか、投資家からクレームがなければ問題にはならないのではないか、税金を払えばいいのではないかと質問を受けることがあります。
しかしながら、そうした考え方は甘く、特段問題が生じていない場合でも、まったくの別件が捜査の端緒になる場合もあります。投資家から苦情が出ていない場合でも、何らかの理由で逮捕されたり、金融庁から警告が発されている例を散見します。
また、税と金融監督は無関係です。高額の納税をしているので、多少の法令違反は許容されるのではないかという意見を散見しますが、納税は国民の義務であり、そんなことは証券監督上、一切考慮されません。おそらく他の行政分野でも同じでしょう。
また、別件から波及する捜査も無視できません。極端な例では、家庭内暴力を最初の契機として、警察に金融商品取引業の無登録営業が立件され、罰金刑に処された事案を見たことがあります。
財務局・金融庁・証券取引等監視委員会は、無登録営業を行う事業者の情報を常に収集しており、いずれも一般から情報提供を受付しているほか、ネット上の情報も監視しています。そのため、ホームページ等でFXや投資顧問等のサービスを無登録で提供している旨を表示すると、早期の段階で当局から警告される可能性があります。
また、証券取引等監視委員会は、無登録業者に対して臨店検査を実施する権限があります。無登録業者に対する検査を通じて金融当局が把握した情報は、必要に応じて警察に提供されており、また悪質な事案、被害額の大きい事案では、前記のように刑事告発を行う場合もあります。
管轄する財務局により刑事告訴の閾となる金額が異なるという指摘もあります。しかし、総じて、悪質性が強いと感じられる事案又は証券市場の根幹を揺るがす事案(例えば、証券会社の顧客資産の分別管理義務に違反した信託財産の流用)は、高い確率で刑事事件化する印象があります。
表示自体も禁止
無登録営業を実際に行うことだけではなく、金融商品取引法上の登録を得ずに、金融商品取引業を行う旨の表示等をすること自体、法律で禁止されています。そのため、ホームページを作って公表した時点で、顧客が一人もいなくても法令違反を構成します。悪意がなく、将来、登録を取得した際に向けてサイトを準備するための、いわゆる「テストサイト」であっても、公開すれば金融商品取引法違反を構成しますので、気を付ける必要があります。
海外ライセンスもほぼ無意味
外国ライセンスを取得することで、日本の登録をしないでも、金融商品取引業に該当する金融サービスを提供することができないかという相談を、事業者から受けることがあります。一般論として、金融機関等の機関投資家向けに業務を行う場合や、国内の証券会社と連携して販売を行う場合等、いわゆるプロ向けの金融ビジネスの場合には、そうしたことが可能になる場合もあります。
しかしながら、ターゲットが一般個人向けで、事業者側も金融機関での十分な職務経験がないようなビジネスでは、海外ライセンスは実務上、無意味です。金融庁は、海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要としています。
いわゆる、外国証券会社(FX業者を含まない)は、国内に拠点を有しない無登録の外国証券業者であっても、例外的に勧誘をすることなく、あるいは第一種金融商品取引業者による代理又は媒介により、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として有価証券関連業のうち一定の行為(金融商品取引法第58条の2及び金融商品取引法施行令第17条の3)を行うことについては許容されています。
しかし、FX業者にはこの特例は定められていないことから、勧誘をしていなくとも国内にある者の注文を受けた時点で金融商品取引法違反を構成します。
なお、外国において日本居住者に対する事業を行う金融関係業者に関する、外国業者の金融商品取引法等の適用の詳細はこちらをご覧ください。
無登録営業の態様
無登録営業がよく見られる類型として、ひとつは海外FX関連です。海外FX業者が居住者に対してインターネット取引を提供するケース、これらのIBとして総客するケース、これに付帯して、PAMM・MAMM等の取引や、自動売買・システムトレード等のサービスを提供するケースなどがあります。
また、バイナリーオプション取引でも、海外FXよりも業界規模と関係者の民度を一段と下げたうえで、ほぼ同様の海外業者による無登録営業スキームが広がっています。
また、平成20年代に一世を風靡したものの、今では相当感度が低い事業者しか行っていない業態として、オフショア地域の海外積立型保険(保険名目ですが実態は集団投資スキーム)の勧誘等もあります。
また、投資助言・代理業も無登録営業が多い業態です。近年、投資顧問サービスを確信犯的に無登録で大規模に行い、捜査当局に立件されたケースもあります。また、システムトレードやツール等の販売や、オンラインサロン等に関しても、無登録で行われることの多い類型です。
さらに、無登録での金集め、すなわち海外ファンドや事業投資の募集その他利殖事案のように、第二種金融商品取引業及び投資運用業の無登録営業が疑われる事案も多く見られます。また、こうしたスキームに、自称コイン、トークン、ブロックチェーンが絡むと、暗号資産交換業の無登録営業の可能性も出てきます。
確信犯的に無登録営業を行うのは論外です。
また、たとえ過失だったとしてもコンプライアンスが重視される現代において、十分なリーガルチェックをせずに無登録営業に至るということ自体に周回遅れ感があります。いまさら、決して格好のいい存在ではないです。時代遅れ感が否めません。
結果的に無登録営業に至ってしまった場合には、早急にこれを是正し、監督当局に対して誠実に経緯と改善策を報告して、適切な善後策を講じていく必要があります。
民事的にも無効
「投資詐欺の法令と被害」の記事にも、その詳細を書きましたが、金融商品取引法第171条の2では、無登録業者による未公開有価証券の売付け等(売付け又はその媒介若しくは代理、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。以下この項において同じ。)付け等は、原則として無効であると定められています。
また、金融商品取引法施行令第33条の4の4(売付け又はその媒介若しくは代理及び募集又は売出しの取扱いに準ずる行為)は「金融商品取引法第171条の2第1項に規定する政令で定める行為は、売出し又は私募の取扱いとする」と定めています。
つまり、無登録業者による既発行有価証券の売付けや売出し、募集又は私募の取扱いは無効であると規制されており、要するに無登録業者からの有価証券取得は、民事的に広く無効主張が可能であることを定めた規定です。
本条文は、訴訟実務上、必ずしも有効活用されておらず、無登録業者を民事的に訴える際には、未だに不法行為構成や債務不履行構成にすることが殆どです。
しかし、実際にはかなり多くの無登録業者による被害事案では、無登録業者による募集又は私募取扱い等が関連しています。そのため、実際には、相手方の無登録営業を、関係当事者に先駆けていち早く疎明するだけで被害回復の可能性が見えてきます。
また、消費者紛争事案では、その他にも、無登録業者による訪問販売による出資契約など、特定商取引法の訪問販売や電話勧誘取引の規制対象である取引様態の場合には、形式的な書面不交付や不備を原因として、無期限の申込等の撤回による元本回復が理論上可能です。
これらは、実際の紛争性事案を担当する実務者にはあまり認識されていませんが、上手くやれば簡単な事実認定と条文操作及び早期段階の仮差押を組み合わせることにより、従来困難であった事案でも、被害回復の可能性が見えてくるのではないかと思えます。
なお、当事務所は、クロスボーダー取引やフィナンシャル・レギュラトリー等の金融法人向け業務を専門としており、無登録業者等による紛争性のある事案は扱いません。消費者の方の相談は一切お受けしませんのでご了承ください。
※当事務所は事業者向けにサービス提供を行っており、消費者相談は行いません。