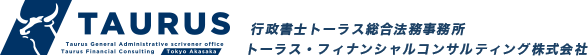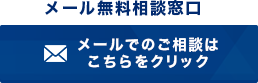2023/04/28
 このページの目次
このページの目次
解釈通知の公表-LPSに関する規制見直し-明示された解釈・有価証券トークン-非有価証券トークン-留意事項-追記(暗号資産投資)
解釈通知の公表
令和5年4月19日、経済産業省は、投資事業有限責任組合(LPS)によるセキュリティトークンへの投資ができることについての解釈通知を公表しました。
経済産業省は、同解釈で、投資事業有限責任組合法の目的たる有価証券をトークン化したセキュリティートークンであれば、みなし有価証券として現物有価証券と同等に扱うことができるため、投資事業有限責任組合の投資対象としても問題ないことを示しています。
LPSに関する規制見直し
投資事業有限責任組合、通称LPSは、株式等の有価証券投資に広く利用されるヴィークルであり、「投資事業有限責任組合契約に関する法律」が設立の根拠法となっています。
同法第3条では「投資事業有限責任組合契約は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる」とされ、投資事業有限責任組合が営むことが可能な事業が列挙されています。
第1号が「株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有」、第2号が「株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は企業組合の持分の取得及び保有」と、主に有価証券への投資を念頭に置いた目的が並んでおり、これら資産に当てはまらない不動産やデリバティブ取引については、主たる目的として投資事業有限責任組合が投資をすることはできないとされています。
しかしながら、現在、同法は規制緩和方向で見直しが進んでいます。
例えば、投資事業有限責任組合が外国株式を取得する際には組合員の出資総額の50%未満とすることが義務付けられていますが、先日には、かかる制限を撤廃する法改正に関する報道がありました。
今回の解釈通知はこれに続くもので、2022年11月に決定された「スタートアップ育成5か年計画」において、「投資事業有限責任組合(LPS)の投資対象について、有価証券をトークン化したいわゆるセキュリティートークン等を扱う事業も対象であることを明確化する」とされたことを受けたものです。
明示された解釈・有価証券トークン
経済産業省は「投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定される事業におけるセキュリティトークン等の取扱いについて」において「LPS法第3条第1項により投資事業有限責任組合が取得及び保有が可能とされる有価証券については、トークン化されたものの取得及び保有も当然に対象事業となると整理することができる。」として、上述のように投資事業有限責任組合法の目的たる有価証券をトークン化したセキュリティートークンであれば、現物有価証券と同等に扱うことを示しました。
なお、ここでは、金融商品取引法及び同法に基づく自主規制用語上の「トークン化有価証券」か「電子記録移転権利」かは、要件に関係ありません。
非有価証券トークン
続いて解釈では「投資事業有限責任組合が、LPS法第3条第1項に掲げる事業のうち、金融商品取引法上の有価証券には該当しない金銭債権、工業所有権、著作権、約束手形及び譲渡性預金証書等を扱う事業を行う場合については、ブロックチェーン等の電子情報処理組織を用いる方法でこれらの資産の移転に係る事務を処理しても、第3条第1項各号に掲げる事業の範囲内で組合契約を遂行するための業務執行と解することができ、第7条第4項に規定する「第3条第1項に掲げる事業以外の行為を行った場合」には当たらない。なお、上記の事務の処理を行うに当たっては、投資事業有限責任組合がこれらの資産を取得及び保有することが前提となる」としており、金融商品取引法上の有価証券に該当しないトークンに関しても、同様に取得が可能であることを示しています。
留意事項
解釈では、経済産業省は、セキュリティートークンが本当に投資事業有限責任組合契約に関する法律の目的の範囲内のトークンであるかは無権代理との関係で注意が必要である旨を指摘しています。
さらに、電子決済手段や、セキュリティートークンと同じくブロックチェーンを利用する暗号資産に関しては、投資事業有限責任組合の投資対象としてはならない旨を注記しています。
投資事業有限責任組合の運営者(無限責任組合員)となる投資運用業者や適格機関投資家等特例業務届出者においては、組合財産からトークンへの投資を行う際には十分な事前検討が必要となります。
4.留意事項
(1)無権代理行為について
投資事業有限責任組合は、組合ごとにLPS法第3条第1項各号に掲げる事業の範囲内において、組合契約によって当該組合の事業範囲を定める(同条第2項第1号)こととされているため、組合によっては第3条第1項各号に規定する範囲よりもさらに事業範囲を限定する場合がある。
無権代理行為は、本人の追認により、本人に対しても効力を生ずるため(民法第113条第1項)、投資事業有限責任組合においても、組合員全員の追認により、当該無権代理行為を有効とすることができる。
ただし、当該無権代理行為が、LPS法第3条第1項に掲げる事業以外の行為である場合については、組合員は追認をすることができないため(LPS法第7条第4項)、当該無権代理行為を追認により有効とすることはできない。
なお、この無権代理行為の責任は、民法第117条に従い処理されることとなり、無限責任組合員は、同条第2項に該当しない限り、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償責任を負うことになる。
したがって、無限責任組合員がセキュリティトークン等を扱う際には、組合契約に定める事業(LPS法第3条第1項に掲げる事業の範囲内)以外の行為も行っていることにならないか留意が必要である。
(2)資金決済法上の電子決済手段及び暗号資産を取得・保有することは、現行のLPS法第3条第1項に掲げる事業のいずれにも該当しない。
追記(暗号資産投資)
令和5年9月16日付の日本経済新聞によれば、政府は、セキュリティートークンのみならず、LPSの投資対象に暗号資産やトークン(電子証票)を加えるとしています。報道によれば、政府は2024年にも投資事業有限責任組合法の改正案を国会に提出するとされています。
内容的に、金融監督当局というよりは、政府与党主導の改正案の印象を受けます。続報を待ちましょう。